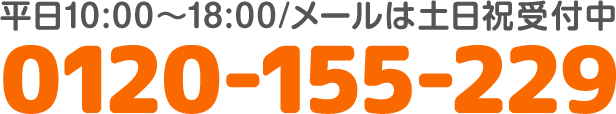芝生に生える雑草の種類と対策6個!雑草だらけでひどい

庭や道端などに生育している雑草は、「雑草魂」という言葉に代表されるように人生の教訓に用いられることがありますね。しかし、実際に自宅の庭などに生えている本物の雑草は繁殖力が高く、何度むしり取っても生えてくるので非常に厄介です。
雑草の種類を知り、それに合った丁寧なメンテナンスを行うことで雑草の繁殖を最大限に防ぐことができます。
ここでは、雑草の種類とその対策、そして天然芝のお手入れ方法についてご紹介します。
※当社では、高品質人工芝の販売・工事を行っています。販売のみもOK。無料サンプル送付可能。どんな人工芝がいいか悩んでいる場合は用途や利用シーンを教えていただければご提案します。ご相談はこちらのページからお気軽にお願いします。
芝生に生える雑草の4種類
道端に生える雑草は、4種類に分けられます。毎年新しい種から発芽・生育する「一年生」の雑草と、地下の根から発芽する「多年生」雑草があり、さらにそこから葉脈が平行になっている「イネ科雑草」と、葉脈が網の目になっている「広葉雑草」に分けられます。
①一年生イネ科雑草
春から夏の高温気に発芽・生育する雑草です。春になると芽を出し、たくさんの種子を飛散してから秋に枯れるものと、越冬し翌年春に繁殖が始まるものがあります。
一度繁殖してしまうと処理が難しい例えば品種で、オヒシバのように茎・葉も丈夫で根が太く、引き抜くのが困難になるものもあれば、メヒシバのように1株で1000粒もの種子を持つとも言われているものもあります。これらは根が太くなる前に抜き取ったり、種を残す前の段階で処理すればば翌年以降は生えてきませんから、小さいうちから処理することが大切です。
一年生イネ科に合う除草剤として、シバゲンDF、ハーレイDF、アージラン液剤、ウェイアップフロアブルなどがあります。
その他の一年生イネ科雑草:シマスズメノヒエ、エノコグサ、イヌビエなど
オヒシバ |
メヒシバ |
シマスズメノヒエ |
エノコグサ |
②多年生イネ科雑草
多年生イネ科雑草の代表的存在ともいうべきスズメノカタビラは、おそらく見たことがない人はいないのではないかというほど、世界中どこにでも繁殖しています。秋には発芽して越冬し、春にも発芽するものもあり、踏圧に強く繁殖する場所を選びません。できれば小さいうちに処理して種の飛散を防ぎたい品種です。
多年生イネ科雑草に合う除草剤は、一年生イネ科と同様、シバゲンDF、ハーレイDF、アージラン液剤、ウェイアップフロアブルなどがおすすめ。
その他の多年生イネ科雑草:ススキ、メリケンカルカヤ、チガヤ、ドクダミ
スズメノカタビラ |
ススキ |
メリケンカルカヤ |
ドクダミ |
③一年生広葉雑草
空気の乾燥したところで生育している一年生広葉雑草は、他の種類の雑草よりも比較的処理しやすいと言われています。見つけ次第早急に処理をしましょう。
除草剤はシバゲンDF、ザイトロンやMCPPが向いています。
その他の一年生広葉雑草:ツユクサ、ブタクサ、トキソウ、カヤツリグサなど
ツユクサ |
ブタクサ |
トキソウ |
カヤツリグサ |
④多年生広葉雑草
品種が多く、処理が最も厄介なのが多年生広葉雑草です。特にハマスゲは、乾燥した場所を好み、世界の強害雑草のトップにも挙げられているほど非常に厄介な雑草で、手作業で引き抜くだけでは処理が難しいのが特徴です。ハマスゲに最も効果的な除草剤はシバゲンDFです。
上記の3種類の雑草に向いている除草剤でも紹介していますが、シバゲンDFはさまざまな種類の雑草に対応しているので、自宅に1つあれば安心です。
その他の多年生広葉雑草:ヨモギ、ハルジオン、ヒメジオン、ハマスゲ、シロツメクサなど
ハマスゲ |
ヨモギ |
ハルジオン |
シロツメクサ |
芝生の雑草対策4個
芝生に生えている雑草は、見た目が悪くなるだけでなく、栄養を奪い、日陰をつくり、芝生の生育を妨げます。最悪、害虫が発生し芝生を傷めてしまう恐れがあるため、こまめな除草作業が必要となります。雑草を除去する以外にも、美しい芝生を維持するためにできる雑草対策をご紹介します。
なお、芝生には高麗芝と西洋芝の2種類があり、一般の家庭では、葉幅が広く西洋芝ほど手がかからない高麗芝が使われていることが多いため、ここでは高麗芝に限定して雑草対策をご紹介します。
①除草剤を使う
ホームセンターや園芸店などで販売されています。雑草処理をする作業を簡略化させ、雑草を生えてこなくする効果がある除草剤もあるので、積極的に活用することをおすすめします。
除草剤には雑草の発芽を抑える土壌処理剤と、すでに生えている雑草に散布して枯らす茎葉処理剤の2種類があります。土壌処理剤は、雑草に対して100の効果を発揮するとしたら、芝生への効果は5くらいと、天然芝への効果が少なく、安心して使用できます。
ただし、あまりにも量が多すぎると、芝生の発育にも影響が出てくるので使用量には注意が必要です。春または秋に散布すれば茎葉処理剤よりも効果があり、長持ちします。
反対に、気温が高い夏または芝生が弱っている時に散布すると薬害が出やすくなり、黄色く変色することもあるので、散布するタイミングを逃さないようにしましょう。そして散布する際は、花や樹木にかからないよう、慎重に作業を進めましょう。
除草剤の売り場を見てみると、「ラウンドアップ」という商品が大々的に販売されていることが多く、除草剤と言えばラウンドアップをイメージする方もいるほどメジャーな除草剤ですが、これは雑草だけでなく、芝生も枯らしてしまうため、天然芝には絶対に使用してはいけません。
そして上記で紹介したように、雑草の種類に合った除草剤を使用しなければ効果が薄れてしまったり、芝生を枯らしてしまったりする恐れがあるため、生育している雑草を把握してから除草剤を選ぶと良いでしょう。
②雑草を抜く

除草剤を使いたくない方や、メンテナンスができる余力のある方は、手で抜き取るのが確実ですし、除草剤で花や樹木を傷める心配もありません。しかし、雑草の繁殖力は想像以上に高く、あっという間に増殖するので、数日に1回あるいは夏の高温期には毎日抜き取らなければ追いつかないかもしれません。
とても根気がいる作業ではありますが、庭や芝生の状態など、芝生の変化に気づきやすく、とても丁寧なケアを行えるのは手作業の大きなメリットと言えます。
なお、雑草の種類によって抜き方にもコツがあります。カタバミやクローバー、ヒメクグなどは、地上で枯れても地下で繁殖を繰り返し、何度抜いても繁殖しつづけます。
このように地下茎で繁殖する多年生雑草は、一度生育してしまったら手作業で根絶させるのは極めて難しいため、除草剤の使用をおすすめします。
③刈り込み

芝生が長い方がふかふかして踏み心地がよさそうに思われるかもしれませんが、実際には芝生の生育のためにも短くしている方がいいのです。芝生があまりに伸びすぎると穂が付き、雑草のように見えるので見栄えが良くありません。それだけでなく、風通しが悪くなることで湿気が高くなり、病気や害虫を発生させる恐れもあります。
芝丈が4cmくらいになったら、刈り込み作業を行いましょう。高さはだいたい1~2cmくらいまでカットします。手動式よりはエンジン式の芝刈り機を利用した方が作業効率アップにつながります。
なお、芝刈り機を動かす方向はいつも同じではなく、時には向きを変えて作業を進めていくことをおすすめします。というのも、一定方向で芝刈り機を入れつづけていくと、芝生にクセがついてしまい、刈り込みがどんどん難しくなるためです。今回は北に向かって刈り込んだから、次回は南に向かって刈り込む、というように常に方向を変えることを意識してみましょう。
刈りカスはそのままにせず、ほうきやレーキなどでまとめてすぐに破棄します。そのままにしておくと病気や害虫が発生するためです。たい肥にして草花の栽培や家庭菜園に利用しても良いでしょう。
芝丈を短くすることで、「見た目がきれいになる」以外のメリットが他にもあります。芝葉の密度が高くなり、地面に日の光が入るのを遮断し、雑草が生えにくくなるので、雑草対策として有効な方法なのです。
刈り込みの頻度は、6~9月の高温期は雑草の成長が非常に早くなるため月に3~4回、毎週のように行いましょう。春と秋は月に2回くらいがベストです。なお、除草剤を使用しない人は、雑草が種をつける時期と芝刈りが重なると種が飛散しさらに雑草が繁殖するので、作業を行うタイミングを間違えないようにしましょう。
④人工芝に変える

※当社の人工芝施工事例
いっそのこと天然芝から人工芝に変える方法もあります。人工芝の品質はここ数年で格段に上がり、見た目が天然の芝生そっくりで刈り込みや雑草むしりなどのメンテナンスが一切不要であることから、気軽に芝生のある庭を楽しみたい方に選ばれています。
人工芝は、芝生を敷く前に、除草剤を使って雑草を枯らし、雑草を完全に除去してから防草シートという日光をシャットアウトする黒いシートを敷きます。これが雑草対策に非常に効果的で摩耗したり、隙間から日光が入らない限りは雑草が繁殖することはありません。
ただし、初心者の方でも気軽に敷けることから、業者に依頼せず、DIYで作業をする方も見られますが、雑草を完全に根絶することは難しく、たいていの方は人工芝を敷いた後に雑草を生やしてしまいます。
多少のコストは発生しますが、プロに依頼すれば土台作りから雑草を生やさないよう、しっかりとした工事を行い、仕上がりも丁寧になるので、人工芝に変える場合はぜひ専門の業者に依頼してみてはいかがでしょうか。
その他の雑草対策2個
芝生のある庭をつくる前の段階から雑草について考慮しておくことも大切です。計画段階から以下の点に留意しておくと、その後の雑草対策が楽になります。
①雑草の生えにくい芝生を使う
トヨタ自動車の関連会社が開発した「TM9」という品種で、通常の芝生より雑草が生えにくくなっています。肥料は通常の芝の半分以下、刈り込みは年に1~2回程度、夏の芝刈りは不要という、メンテナンスも楽になる品種で、天然芝にこだわりたいけどメンテナンスが面倒と感じている方におすすめです。
②日当たりのいい場所を選んで芝生を敷く
水や除草剤、肥料などの芝生のお手入れは人力で対処できるものです。しかし、日当たりに関しては自然の力に頼るほかなく、人の力で何とかできるものではないため、計画段階で日当たりをよく確認しておきましょう。午前中のやわらかい光が5時間以上当たる場所がベストです。
日当たりの悪い場所では、生育が悪くなり、雑草が生えやすくなるため、もし芝生の敷設箇所が日当たりの悪い場所なら、天然の芝生を諦めて人工芝に変えることも検討してみましょう。他にも砂利やタイル張りなど、芝生以外の施工を選んでみてはいかがでしょうか。
天然芝の手入れ方法
天然芝は、季節に合った手入れを丁寧に行えば何十年も綺麗な状態を維持できます。雑草の処理と刈り込み以外に忘れずに作業してほしいことがあります。
水やり
朝と夕方にたっぷりと与えましょう。日当たりと風通しも気にしながら芝生に均等に水分を行きわたらせます。ホースによる水やりでもかまいませんが、スプリンクラーなら機械によって自動で水やりをしてくれるので便利です。
肥料をまく
芝生に適した肥料を芝生全体に、均等に行きわたらせるように肥料をまきましょう。春から秋にかけて月に1回程度、夏は通常の半量を月に1回くらいの頻度がおすすめです。
まとめ
天然芝と雑草は、切っても切れない関係にあると言っても過言ではありません。しかし、細やかなケアを続ければ、雑草の繁殖を防ぐことができ、自分で育てている芝生に愛着が湧くというものです。雑草の種類とそれに合った除草剤と対策方法を知ることで、きれいな芝生のある庭を楽しんでみてください。