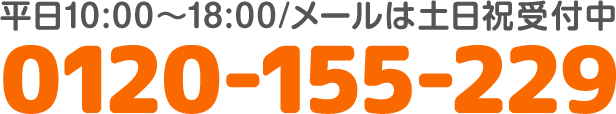人工芝は水はけが悪い?人工芝の水はけを良くする対策5個

庭やベランダなどに人工芝を導入したいと考える人も多いでしょう。しかし、人工芝は水はけが悪いのではないかと懸念して、二の足を踏んでいる人も少なくありません。
実際のところ、人工芝の水はけは悪いのでしょうか?また、水はけが悪い場合の対策法が分かっていれば、安心です。
今回は、人工芝の水はけについて解説します。
※当社では、高品質人工芝の販売・工事を行っています。販売のみもOK。無料サンプル送付可能。どんな人工芝がいいか悩んでいる場合は用途や利用シーンを教えていただければご提案します。ご相談はこちらのページからお気軽にお願いします。
人工芝は水はけが悪い?
人工芝と聞くと、水はけの悪さをイメージして嫌厭する人も少なくありません。人工芝は様々なメーカーから発売されていますが、多くのメーカーではしっかりと水はけ対策を施しています。そのため、人工芝自体は水はけが悪いわけではありません。
しかし、問題となるのは人工芝を敷く土台です。例えば、ベランダに人工芝を導入する場合の多くは、コンクリートが土台となります。そもそもコンクリートは水はけが悪いため、いくら水はけの良い人工芝をおいても同じことです。
また、庭に敷いたとしても、水はけの悪い土地が土台となる場合は要注意です。こうした土台に人工芝を敷く場合は、より一層水はけの良い製品を導入しなくてはなりません。
中には、水はけの悪い人工芝もあるため、気をつけましょう。特に、昔から使われてきたような人工芝は、水の浸透性が低いため、カビの発生やホコリが溜まる原因になります。
水はけが良い人工芝の特徴

※弊社の商品例
水はけの良い人工芝は、透水性があることがポイントです。最近売られている人工芝のほとんどは、裏面に水抜きをするための穴が空いています。
人工芝の表面に溜まった雨水は、この穴を通して排水されるので、水はけの悪さが解消されるので安心です。
また、水抜き穴が空いていないと、排水性の悪さからカビや苔が生えるのはもちろん、通気性が悪くなるため、ゴキブリなどの害虫が発生する要因になりかねません。
加えて、耐久性も気になります。人工芝の素材は、ポリエチレン製とポリプロピレン製が定番です。ポリプロピレンはリーズナブルな素材ですが、耐久性の面からいえばポリエチレンが高いでしょう。
人工芝を選ぶ際は、水はけ用の穴が空いているかを確認することと、素材をチェックすることが大切です。
人工芝の水はけを良くする改善対策5個

せっかく人工芝を敷いたけど、あまり水はけが良くなくて悩んでいる人もあるでしょう。そんな時におすすめの改善対策を5つ紹介します。
1. ジョイントタイプを選ぶ
人工芝にはロールタイプとジョイントタイプの2種類があります。
ロールタイプとは切れ目のない人工芝で、つなぎ目が少ないと言ったメリットがあるものの、水はけの面では隙間がない分溜まりやすくなるでしょう。
一方のジョイントタイプは、タイルのように繋げて使う人工芝なので、パーツとパーツの間に隙間が空き、水はけが良くなり通気性も高くなります。
また、ロールタイプは地面に密着するものが多いですが、ジョイントタイプはマットの下に足がついているものが多いため、土台との間に隙間が空く点もポイントです。
施工費で見るとロールタイプの方がリーズナブルですが、長い目で見たときにメンテナンスを考えるとジョイントタイプの方がコスパが高いでしょう。
2. 芝の長さが短いタイプを選ぶ
人工芝は、種類によって芝の長さも異なります。芝の長さが長いと、クッション製も高い印象があり、魅力的に感じる人も少なくありません。しかし、水はけを考えると芝が短いものをおすすめします。
芝の長さが長いと、湿気や水が溜まりやすくなり、水はけ対策にはなりません。
水はけの良い人工芝は、芝の長さが1cmより短いタイプです。短めの人工芝であれば、通気性や排水性はもちろん、汚れも溜まりにくくなるので掃除がしやすくなります。
また、芝の長さが短い人工芝は、価格も長いものよりリーズナブルなのでコストも抑えられるのも魅力です。
3. 土台に傾斜をつける
水はけの悪い土台に人工芝を敷く時は、傾斜をつける方法があります。いわゆる「表面排水」という方法です。
特に、コンクリートが土台となる場合、土とは違い水を吸収しません。いくら水はけがよく裏に穴が空いている人工芝を使っても、地面の排水が悪ければ、水が行き場を失い水たまりができてしまいます。
表面に緩やかな傾斜を作ることで、溜まった水が流れやすくなります。流れた水は、排水管に向けて集まるようにしなくてはなりません。水は、高いところから低いところに流れる性質があるので、土台となる地面に合わせて傾斜をつけましょう。
4. 落葉樹に気をつける
実は、人工芝は落葉樹との相性があまり良くありません。大きな葉っぱや針葉樹であれば、落ち葉が拾いやすいため、そこまで問題視する必要はありませんが、小さい葉っぱは特に注意が必要です。
乾燥した小さい葉っぱを踏むとバラバラになり人工芝の隙間に入り込みます。雨や水やりの際に水がかかれば、隙間に入り込んだ葉っぱの破片が、人工芝の裏面にある穴に詰まる可能性があるでしょう。そうすると、流れるべき水が溜まってしまい、水はけが悪くなります。
落葉樹を植える時は、葉っぱが落ちることを考えて植えるように気をつけましょう。
5. 防草シートも透水性があるものにする
人工芝といえば、ネックになるのが雑草です。そのため、人工芝の土台となる部分が土の場合、雑草対策を施さなければなりません。
基本的に雑草対策をする際には防草シートを貼りますが、防草シートの水はけが悪ければ、人工芝自体が水はけの良いものでも水が貯まりやすくなります。
快適に人工芝を使うためには、透水性のあるものを選びましょう。穴が空いた人工芝専用の防草シートも販売されているので、チェックしてみることをおすすめします。
コンクリートの人工芝の水はけ対策
基本的に、ベランダや屋上などは水はけを考えた設計がなされています。とはいえ、地面に水が浸透するわけではないので、土や砂のような水はけは期待できません。
人工芝を敷く時に水はけが気になる場合は、下にすのこを敷くと良いでしょう。すのこを敷くことで、人工芝自体に水が溜まることを避けられます。
また、ロールタイプよりジョイントタイプがおすすめです。人工芝が汚れたり、排水のための穴が詰まったりした場合、該当箇所だけを外して手入れができるため重宝します。
室内の人工芝の水はけ対策
室内でも人工芝の水はけは欠かせません。外のように雨が降るわけではありませんが、湿気が溜まることが考えられるためです。室内でも湿気がたまれば、カビの原因となります。
そのため、室内に人工芝を敷く場合も、必ず排水性の高いものを選びましょう。外で使うものと同じく、裏に穴が空いているタイプがおすすめです。
徹底的に湿気対策を施したい場合は、人工芝の下に除湿シートを敷く方法があります。また、定期的に人工芝を取り除いて、カビが生えていないかチェックしてメンテナンスするように心がけましょう。
まとめ
最近の人工芝は、水はけのことを考えた作りになっています。しかし、日当たりが悪い場所やそもそも土台の水はけが悪ければ湿気がこもりカビが発生する可能性も否めません。
快適に人工芝を敷く為に、しっかりと土台を整えることが大切です。また、定期的なメンテナンスも欠かさないように心がけましょう。